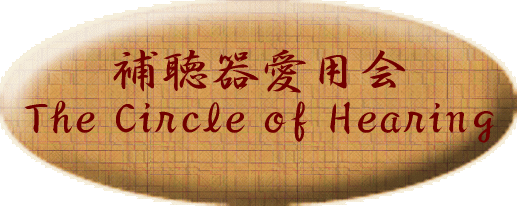�@�@�@�@
�⒮��̕��y�Ɋւ��鎄��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����17�N4��8��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���I�l�b�g�Z���^�[����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ꎓ��@�C
�@���{�Ɖ��āA���ɕč��Ƃł͕⒮��̏o�ב䐔�ł͐l���ɑ��Ė�2�{�č��̕��������Ƃ����Ă���B
���̎�ȗv���Ƃ��ẮA
�P�D�������p���������B
�@�č�70���`75���A���{10�`20���i���m�ȓ��v�͂Ȃ����o���I�Ȑ��l�j�Ɠ��{���Ⴂ�B
�@�č��Ɠ��{�̕⒮�핁�y��(�����ɂ͏o�ב䐔)�̑傫�ȈႢ�́A�Ў��݂̂ɕ⒮��p���邩�A������
�@�⒮��p���邩�A�����闼�����p�����傫���قȂ邱�Ƃł���B
�@�������p���̓��ĂňقȂ�v���Ƃ��āA
�@�@�@����ҁi��ҁj����я���҂���芪�����������̗������p�ɑ���ӎ��̈Ⴂ�B
�@�@�A�������p�̔�p���S�ɑ���S���I��R��(���@�Ȉ���܂�)�B
�@�@�B�������p�̗L�����i�������ʁj�̕s���B
�@�@�C�i�Љ�Ƃ킪���̘a�̎Љ�ɑ�\����镶���̈Ⴂ�B
�@�@�@�@�č��̎���Ƃ��āA�⒮��̔��X���Ў����p�Ƃ�����ŁA�p���������ʎ��̑������ڋq���̔��X��
�@�@�@�@�i�����B�������p�����߂��Ȃ玖�̂͋N���Ȃ������\���������Ƃ��āB
�@�@�@�@���̎���ȍ~�̔��X�͕K���������p�����߂邱�Ƃ��K�v�ɂȂ����B����͗������p�����߂��`�����ɂ�
�@�@�@�@�Ȃ������Ƃ������ł���B
�@�@�@�@����킪���ł́A���ɕč��̂悤�Ȏ��Ⴊ�����Ă��i�ׂɂ͂Ȃ�ɂ����A�a�������āi�b�������āj��������
�@�@�@�@�Љ�y�̂悤�ł���B����́A���ĕ��݂̊�������邩������Ȃ��B
�@�@�D�č��͓��{�ɔ�ׁA�⒮��s��͉ߓ�������Ԃł���B����Ĕ̔��̔M�ӂ������B
�@�����̑Ώ��Ƃ��āA����҂���芪�������������܂ߗ������p�̗L�����̌[�֊����A�����w�����̉��i����A
�@�������p�Ɋւ��錤���̋������s���K�v������B
�Q�D�⒮��̔��X�̑���
�@�⒮��̋������_�i�̔��X���j���č��̕������|�I�ɑ����Ƃ����Ă���B
�@�č��ł͕⒮��̔̔��X�i�⒮��̋������_�j�́A�킪����5�{2.5���X(�킪���ł́A�⒮��������Ă���X�́A
�@�d�b�����̑��Œ��ׂ�ƍő��5000�X)�Ƃ����Ă���B����ɕč��ł́u�}�N�h�i���h�̂��钬�̋K�͂ł����
�@�⒮��X������B�v�Ƃ�����悤�ɏ����Ȓ��ɂ����݂���Ƃ������A�����l�̐l��������Ε⒮��X������
�@�����Ă���悤�ł���B��������������Ε��y���Ƃ����ϓ_�Ō�������Ȃ��Ă���B
�@�䍑�ɂ�����⒮��̏o�א��ʂ́A����6�N�ɂ�33���䋭�ł��������A����16�N�ɂ�465,261��ł������B
�@�I���������̃C�����C�g�A�~�~�[�d�q������т������⒮�퇊���A�L���ӔC���Ԗ@�l���{�⒮��H�Ɖ�ɖ�����
�@���[�J�[�̐��Y���𐄒�ł��邪������A����16�N�̕⒮��o�ב䐔��57����`60����Ɛ���ł���B
�R�D�s��K�͂̔�r
�@�č���200����o��(2004�N 2,146,095��)�́A�l�������{�̖�2�{�Ƃ���A���{�̐l���Ɋ��Z�����100����
�@�ƂȂ�B
�@�������p����č�75���A���{15%�Ƃ���A�⒮��p���Ă���g�l�h�̐��Ƃ��Ă݂�Ȃ�Έȉ��̂悤��
�@���������(�A���č��̑��p�҂���{�̐l����Ɋ��Z����)�B
�@�č���2003�N�̕⒮��w���ҁ�
�@�@���i2003�N�⒮��o�ׁ~�������p���j��2��2�j�{�i2003�N�⒮��o�ׁ~�Ў����p���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��1)���ʍɁA�\���̍w�����͍l�����Ă��Ȃ��B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��2)�������p���g�l���h�ɂ����1�l�ł���B
�@���č���2004�N�̕⒮��w���ҁ��i2004�N�⒮��o�ׁ~0.75�j��2�{�i2004�N�⒮��o�ׁ~0.25�j
�@�@���i100�~0.75�j��2�{�i100�~0.25�j��62.5���l
�@�̂ɕč��ł�62.5���l�́g�l�h���V���ɕ⒮����w�������������ւ������ƂɂȂ�B
�@���l�ɓ��{�ł́A
�@���{�̍�N�̕⒮��w���ҁ��i2004�N�⒮��o�ׁ~0.15�j��2�{�i2004�N�⒮��o�ׁ~0.85�j
�@�@���i46.5�~0.15�j��2�{(46.5�~0.85�j��43���l
�@�ȏ�̂��Ƃ���č��Ɠ��{�̎s��ŕ⒮����w�����������́g�l�h�̍��́A62.5�|43��19.5���l�ƂȂ�B
�@�ȏ�̊ϓ_���猩��ƕč��̕⒮��̕��y��(�⒮�푕�p��)�́A62.5��43��1.45�ƂȂ�A���{��1.45�{�ł���B
�S�D���{�̕⒮��̕��y�������コ����ɂ�
�@���{�̕⒮��̕��y�������コ���邱�Ƃ��d�v�ł��邪�A�Ƃ肠�����A���{�̕⒮��s���č����ɂ��邱�Ƃ�
�@�l���A���ɕ��y���̌����ɂ��čl���Ă݂����B
�@�č��̎s��K�͂Ɠ��{�̂���́A��L��1.��2.���傫�ȈႢ�Ǝv����B���ɓ��{�̔̔��X�́g���h���������Ƃ�
�@�Ȃ��Ǝv����B�̔��̎��ɂ��ẮA�}�N���I�Ɍ���Γ��č��͂Ȃ��Ǝv����B
�@���������ĂƂ��ꕔ�̔̔��X�ɂ����Ă͏���҂��Ȃ�������ɂ����̔����s���Ă���B���̌��ʕ⒮���
�@���]���ɂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ������ł���i�č��ɂ�����m�[���Y�Ђ̒���������č��ł�����Ȃ�ɖ���
�@��������j�B
�T�D�⒮��̐��ݎ��v�ƌ��ݑ䐔�i�⒮��͉䂪���ʼn��䂭�炢�ғ����Ă���̂��낤���B�j
�@����č����ł͂Ȃ��⒮��̐��ݎ��v�����݉������邽�߂̎{����l����K�v������B
�@�����V���̋L���i2005�N3��2���t�u�����ɍ������⒮����v�j�ɂ����[�J�[�A�����ƊE�c�̂����Ғc�̂�
�@��\�҂�ł���u�⒮�틟���V�X�e���݂̍��������v�i��\�A�͖�N���E���a���q����C�����j����N���\����
�@�ł́A�⒮��̐��ݎ��v�͐l���̖�15.4%�Ƃ����A�䂪���ł͖�1944���l�Ƃ��Ă���B ��3�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@*3)�ʂ̎����ł͐l����5���A600���l�Ƃ������Ă���B
�@���݁A���{�����ŕ⒮��͉��䂭�炢�ғ����Ă���̂��낤���B
�@����ɂ��Ă̓��v�����͊F���Ǝv����B�����ł��Ȃ�r���ۂ����ȉ��̂悤�ȉ���̊�ɐ������Ă݂��B
�@�@����@�@1�N�Ԃɏo�ׂ��ꂽ�⒮���43����i�ߋ�5�N�Ԃ̕��ϒl�j���Ƃ���B
�@�@����A�@���N�x�o�ׂ��ꂽ�⒮��̗��ʍɂ�10���Ƃ���B
�@�@����B�@�S���[�J�[���o�ׂ��ꂽ�⒮��́A���̔䗦�Ŏg�p����Ă���Ƃ����B
�@�@�@�@�@�@���N�x�o��80���i���ʍɂ��܂ށj�A�O�N�o��80���A2�N�O�o��75%�A3�N�O�o��50%�A
�@�@�@�@�@�@4�N�O�o��35%����ȑO�̂��̂̍��v15%�Ƃ����B
�@
�@�@2�~(43�~0.8�j�{�i43�~0.75�j�{�i43�~0.5�j�{�i43�~0.35�j�{�i43�~0.15�j��144�i����j
�@�@144�i����j�̂����������p�҂��l�������144-(144�~0.15��2�j��133���l�ƂȂ�B
�@�������ɂ݂�ƕ⒮��̌��ݎ��v����133/1965�~100��6.84(%)�Ɛ����ł��A�⒮��̌��ݎ��v�͂���߂�
�@�Ⴍ�A�����̎��҂̌���Ƃ���Ƒ卷�Ȃ��Ǝv��ꂽ�B
�U�D�⒮��̕��y����
�@���̂悤�ȏ���A�⒮��̕��y�ɂ́A�⒮��̗L�p���Ƌ��ɁA�y�x��҂̈ӎ��i�����Ȃ����Ƃ̕s�ւ��A
�@���l�����f�����Ă��邱�Ƃւ̗����A���̑��j��ς��邱�Ƃ��d�v�Ǝv����B
�@�ӎ��͓�҂���芪�����͂̕��X���܂߂�K�v������B���̂��Ƃ̓��C�t�f�U�C���������̃��|�[�g�ł�����
�@���ł���B
�@�⒮����w��������X���⒮��p���铮�@�ɁA�u�Ƒ���m�l���犩�߂��āv�y�� �u�������g����v��
�@�������߂Ă���B�܂��A���@�Ȉ�ɓ�ɂ��đ��k�������ʁA�u�⒮��X���Љ�ꂽ�v���Ƃɂ���ĕ⒮���
�@���\��⒮��X���ǂ��ɍ݂邩��m�����P�[�X����������B
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ�����A��ҋy�ѓ�҂���芪�����͂̂����������܂߁A�⒮��ɂ��Ă̗L�p���ƕ⒮��
�@�X���ǂ��ɍ݂邩��m�点�邱�Ƃ͏d�v�ł���B
�@�����̕⒮��w���҂́A�����ǂ��ŗǂ��⒮��i�����̓�ɓK�����j���w��������悢����m���Ă��邱�Ƃ�
�@���Ȃ��B�ዾ�X�͋��Z���钬�̎��ӂɂ��Ȃ葶�݂��Ă��邪�A�⒮����X�͏��Ȃ��̂�����ł���B���܂���
�@�ዾ�X�ŕ⒮����������w������ڋq�����Ȃ葶�݂���B
�@�ʔ̂ōw��������X�̍w�����@�ׂ����Ƃ͂Ȃ����A���i�������������w��������@�����m�Ȃ��Ƃ������
�@�v����B
�@����A�⒮��p���Ȃ��v���Ƃ��āA
�@�@�@�⒮��͎G������Ŋ̐S�ȉ����������Ȃ��B
�@�@�A�⒮��͊ዾ�̂悤�ɑ��p�����璼���ɗǂ������邱�Ƃ��̊��ł��Ȃ��B���n�r���e�[�V�������K�v�ł���B
�@�@�@�i�ዾ�́A�œ_�ُ���������邱�Ƃ͂ł��Ă��A������A�Γ���A�Ԗ��⎋�_�o�ُ̈�ɂ͎g���Ȃ��B
�@�@�@�⒮��́A�Ԗ��ɑ�������嗋��̏�Q�ɑΏ����邱�Ƃ������B
�@�@�@�œ_�ُ�́A���o�ł́A�`����ɑ������A���̓�ɂ͑傫�Ȍ��ʂ����邱�Ƃ͏��m�̂Ƃ���ł���B�j
�@�@�B��Q�҂�V�l�Ɍ���ꌙ�ł���i��҂̒��ɂ́A�����͎�����������Ƃ�ϋɓI�ɑ��l�ɗ�������
�@�@�@���炢�b�����ɔz�����肤���X���������邱�Ƃ������ł���j�B
�@�ȏ�̂悤�Ȕw�i����A�⒮��̕��y�ɂ́A
�@�@�@�⒮��̗L�p����PR����i����͏]���s�Ȃ��Ă���j
�@�@�@�d�v�Ȃ̂̓��[�J�[�̋Z�p�҂��܂ߕ⒮��̋����Ɍg���l�X�́A�ڋq�d���́g�S�h�̋���ł���B�g�S�h��
�@�@�@����ł͂Ȃ��Ȃ��|���Ȃ����w�͕͂K�v�ł���B�g�S�h��|�����ƂŁA�ڋq�Ƒ�����⒮��X�������
�@�@�@�����ł��⒮��͗L���Ȋ�@�ł��邱�Ƃ𗝉����Ă����������Ƃ��d�v�ł���B
�@�@�@�⒮�킻�̂��̂̐��\�̂ق��ɁA�⒮��͋����Ҏ哱�̏��i�ł��邱�Ƃ���u���悾���Ŕ������ꂽ�v
�@�@�@��ۂ��⒮��̈���ۂɂ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ����Ȃ��炸����B
�@�@�A�⒮��X�̑��݂�PR����i����͏]���s�Ȃ��Ă���j�B
�@�@�B�⒮��̉��i�т��L���A�ቿ�i���i�̔̔��ɗ͂�����B�ʔ̂́g�⒮��h���邢�́g�W����h�͋C�y��
�@�@�@�w���ł��邪�A�⒮��̉��i�ł͍w���ɐK���݂�����B
�@�@�C�⒮��X�𑝂₷�B
�@�@�@���ʌo�H�̐V���ȊJ�K�v�ɂȂ�B�����̃��[�g�ł͂�����x���E�������Ă���B
�@�@�@���ɂ͏����Ȓ��ł��i���ʐl��5���l���邢�͐����l���x�̓s�s�j�⒮��X�𑝂₷�B���̂��߂ɂ͏��Ȃ�
�@�@�@�̔��䐔�ł��o�c�����藧���Ƃ��d�v�ł���A���̖ʂ�����č����݂̃I�[�_�[���C�h�⒮��̔̔����i�A
�@�@�@�f�W�^���⒮����܂߂����t�����l���i���������Ƃ��K�v�ɂȂ�B
�@�@�@����͕⒮��̉��i�т��L���邱�ƁA�V���[�g�Ƃ̊W���܂ߏ��n�̌��Ƃ��Ȃ�B
�@�@�D�������p�������߂�B
�@�@�@�������p�̗L������⒮��X�ɋ��炵�A���悾���̗L�p���ł͂Ȃ��A�ڋq�ɏ\�����������邱�Ƃ��ł���
�@�@�@�m���ƃt�B�b�e�B���O�̋Z�\���C��������B�\���̕⒮������߂��藼�����p�����߂�B
�@�@�E�⒮��X�̈ꗗ�\���J�^���O�Ƌ��ɔz�z���铙�⒮��X�̑��݂�m�点��H�v���K�v�ł���B
�@�@�F��莿�̍����⒮��y�ѓ���ɑ���m���y�ѕ⒮��̃t�B�b�e�B���O�Z�\�����炷��B
�@�@�G�f�W�^���Z�p����g���A�R�X�g�p�t�H�[�}���X�̍����⒮��̋����ɂ��u�⒮��͖��ɗ��v
�@�@�@���Ƃ�PR���Ă����B
�@�@�H�ʔ́A�����킠�邢�͏W����̗ނ́A�⒮��p���邫��������^������ʂ��傫���B
�@�@�@�����̏o���ŕ⒮��̏o�ב䐔�������Ă���Ƃ͎��ɂ͎v���Ȃ��B�ʔ̂̕⒮����̔����������Ă��邪
�@�@�@�⒮��̏o�ׂ������X���ɂ���B
�@�@�I�⒮��̗L�p���ɂ��ĕ⒮��p����Ă�����X�̑�����������i���Ă��������B
�@�@�@�⒮�툤�p��̃z�[���y�[�W�͂܂��ɐ������˂��Ă���Ǝv���܂��B
�@�@�J�⒮�틟���ґ��i���[�J�[�y�є̔��X�j�́A��̂��������Ɍ����^����悤�ȁA�������`���T��������
�@�@�@���Ǝg�p�ґ��o���̃��j�^�����O�i�Ď��j���K�v��������Ȃ��B
�@�ȏ�̍��ڂ�L���ӔC���Ԗ@�l�@���{�⒮��H�Ɖ�A�L���ӔC���Ԗ@�l�@���{�⒮��̔��X����y��
�⒮�툤�p����͂��ߑ����̓�҂̉�Ƌ����ōs�����邱�ƂŌ��ʂ��{�����A���낢��ȍL���������ݎ��v�҂�
�����I�ɓ`��蕁�y���ʂ�����Ǝv����B
�ȏ�⒮��̕��y�ɂ��čl���Ă݂������ʂƂ��č��܂ł���ꂽ���Ƃ̈���o�Ȃ������B
�@���Q�l������
�@�@�@�č��̕⒮��o�ב䐔�́ATHE HEARING REVIEW MARCH 2005 P18�@Reasons for Optimism:
�@�@�@A Look at the 2004-2005 Hearing Instrument Market"�ɂ��B
�@�@�@�@
�⒮��̎��ғ��䐔�\��
�i�⑫�����j
�@�⒮��̏o�ב䐔�y�ы�C�d�r�̏o���͂��ꂼ��̍H�Ɖ�玦���ꂽ���l�ł��B
���̐��l����ɂ킪���ɂ�����⒮��̎��ғ��䐔��\���������܂����B
�䂪���ɂ�����⒮��̉ғ��䐔�͖�144����A�ʔ͖̂�35����A���v��180�����Ɛ���ł��܂��B
�⒮��p�̋�C�d�r�͔N��41,827��i41.5�~10
�ȉ��Z�o�����ɂ��Ď����܂��B
�ߋ�11�N�Ԃ̕⒮��o�ב䐔�͕\�Ɏ����Ƃ���ł��B���̐��l�͗L���ӔC���Ԗ@�l���{�⒮��H�Ɖ��
�������Ă��郁�[�J�[�����ꂽ���̂ł���A������̃��[�J�[�͊܂܂�Ă��܂���B
| �N | 1994�N | 1995�N | 1996�N | 1997�N | 1998�N | 1999�N | 2000�N | 2001�N | 2002�N | 2003�N | 2004�N |
| �䐔 | 333,812 | 391,682 | 407,919 | 412,626 | 403,183 | 400,659 | 413,736 | 412,094 | 428,211 | 447,757 | 465,261 |
�@�ʐM�̔��ɂ��⒮��y�яW����i�ȉ��ʔ̂Ɨ����j���̏o�ד��v�͂Ȃ��̂ŕs���ł��B
������ɂ��Ă������̕⒮�킪�A�ғ����Ă���Ǝv����䐔��\���������v�I�f�[�^�[�͊F���Ǝv���܂��B
�����ł��Ȃ�r���ۂ��\���ł��邪�ȉ��̂悤�ȉ���̊�ɗ\�������݂܂����B
�@����@�@���N�̏o�ב䐔��43����Ƃ���i�ߋ�6�N�Ԃ̕��ρj�B
�@����A�@�ʔ̂̔N�ԏo�ב䐔��15����Ƃ����B�ʔ͉̂ߋ�4�N�Ԃ�Ώۂɂ����B
�@�@�@�@�@�@�ʔ̂̔N�ԏo�ב䐔��15����Ɖ��肵���̂́A�V�����ւ̍L���f�ڕp�x�A�̔����i�����l�������B
�@�@�@�@�@�@15����͍T���߂Ǝv����B�����̏��i�̔̔����@��A�t�^�[�t�H���[�̏���ғ����͗\�����
�@�@�@�@�@�@�Ⴂ��������Ȃ��B�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�u�⒮�틟���V�X�e���݂̍���Ɋւ��錤���v3�N�����u�K���ȕ⒮�핁�y�̂��߂̋����V�X�e��
�@�@�@�@�@�@�Ɋւ��钲�������v��P34�ɂ͒ʔ̂̐��ʂ��u2003�N�̔̔����т�A���ʊ֓��v�y�і��Y����
�@�@�@�@�@�@���v���v���琄�肵15�`20����Ƃ��Ă���B
�@����B�@�⒮��́A���N�x�o�ׂ������̂�10���͗��ʍɂƂ����i����A�I�[�_�[���C�h�⒮�킪���������
�@�@�@�@�@�@���ʍɂ͌�������j�B
�@����C�@�⒮���1������7���Ԏg�p�B�ʔ̂�1������2���Ԏg�p�Ɖ��肵���B
�@����D�@�⒮��S�̂��炻�ꂼ��̕⒮��̐�L���́A�|�P�b�g�`�⒮��10���A�������`�⒮��40���A�����Ȍ`
�@�@�@�@�@�@�⒮��i�I�[�_�[���C�h�⒮����܂ށj50���Ƃ����B
�@����E�@�ʔ̂́A��C�d�r�g�p�̕⒮��́A�S�̂�70���A���d�r�g�p��30���Ƃ����B
�@����F�@�o�ׂ��ꂽ�⒮��͎��̔䗦�Ŏg�p����Ă���Ƃ����B
�@�@�@�@�@�@���N�y��2�N�O�͗��ʍɁA�\���Ƃ��čw�������⒮�퓙���l���o�ׂ��ꂽ�⒮���80�����ғ�����
�@�@�@�@�@�@����Ɖ��肵���B�I�[�_�[���C�h�⒮��̕��y����80���̉ғ�����90�����炢���Ó���������Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@���N�@80���A2�N�O�@80���A3�N�O�@75���A4�N�O�@50���A5�N�O�@35���A6�N�ȑO�̂��̂̍��v15���Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@�ʔ̂́A���N90���A2�N�O�@70���A3�N�O�@40���A4�N�O�@20���Ƃ����B
�@�@�@�@�@�@�ʔ̂̉ғ����͕⒮��Ɣ�����Ǝv���邪���̂悤�ɉ��肵���B
�P�j���ݎg�p����Ă���Ɖ���ł���⒮��̑䐔�́A
�@�@�@�@N�P=2 (43�~0.8)+(
43�~0.75)+(43�~0.5)+(43�~0.35)+(43�~0.15)��144(����)
�@�@�A���ʔ̑䐔N�Q�́A
�@�@�@�@N�Q= (15�~0.9)+(15�~0.7)+ (15�~0.5)
+(15�~0.2)��35(����)
�@�@�ʔ̂�������Ɓ@144�{35��179��180(����)
�Q�j1�N�Ԃɕ⒮��y�ђʔ̂����삵�Ă��鉄���ԃ�Hrs�́A
�@�@�⒮��́A1������7���ԓ��삵�Ă���Ɖ��肷��A
�@�@�@�@��Hrs��144�~10![]() �~�V�~365��3,679�~10
�~�V�~365��3,679�~10![]() �i��rs�j
�i��rs�j
�@�@�ʔ̂�1�N�Ԃɕ⒮�킪���삵�Ă��鉄���ԃ�Hrs2�́A
�@�@�ʔ̂�1������2���ԓ��삵�Ă���Ɖ��肷��A
�@�@�@�@�@�@��Hrs��35�~10![]() �~2�~365��256�~10
�~2�~365��256�~10![]() �i��rs�j
�i��rs�j
�R�j��Hrs�����ꂼ��̕⒮��`��̔䗦�ł݂�ƁA
�@�@�@�⒮��́A
�@�@�@�@�|�P�b�g�`�⒮��(���d�r)��3,679�~10![]() �~0.1=367.9�~10
�~0.1=367.9�~10![]() ��370�~10
��370�~10![]() �i��rs�j
�i��rs�j
�@�@�@�@�������`�⒮��(��C�d�r)��3,679�~10![]() �~0.4=1,471.6�~10
�~0.4=1,471.6�~10![]() ��1,470�~10
��1,470�~10![]() �i��rs�j
�i��rs�j
�@�@�@�@�����Ȍ`�⒮��(��C�d�r)��3,679�~10![]() �~0.5=1,839.5�~10
�~0.5=1,839.5�~10![]() ��1,840�~10
��1,840�~10![]() �i��rs�j
�i��rs�j
�@�@�@�@�������`�y�ю����Ȍ`�⒮��(��C�d�r)��(1,470+1,840)=3,310�~10![]() �i��rs�j
�i��rs�j
�@ �@�ʔ̂́A
�@�@�@�@�|�P�b�g�`(���d�r)��256�~10![]() �~0.3=76.8�~10
�~0.3=76.8�~10![]() ��77�~10
��77�~10![]() �i��rs�j
�i��rs�j
�@�@�@�@�������`�y�ю����Ȍ`(��C�d�r)��256�~10![]() �~0.7=179.2�~10
�~0.7=179.2�~10![]() ��180�~10
��180�~10![]() �i��rs�j
�i��rs�j
�S�j�d�r�̌`��ł݂�ƁA
�@�@�@���d�r�̑��ғ����ԁ�(370+77) �~10![]() ��447�~10
��447�~10![]() �i��rs�j
�i��rs�j
�@�@�@��C�d�r�̑��ғ����ԁ�(3,310+180) �~10![]() ��3,490�~10
��3,490�~10![]() �i��rs�j
�i��rs�j
�T�j���d�r�Ƌ�C�d�r�̔N�ԏ���ʗ\��
�@�@�@�⒮��́A
�@�@�@�@1�́A1��7���Ԏg�p��14���Ԏg�p�ł���Ɖ��肷��B
�@�@�@�@1�̓d�r���g�p�ł��鎞�ԁ@�V�~14��98��100�i��rs�j
�@�@�@�ʔ̂́A
�@�@�@�@�d�r1�́A1��2���Ԏg�p��7���Ԏg�p�ł���Ɖ��肷��B
�@�@�@�@1�̓d�r���g�p�ł��鎞�ԁ@2�~7��14�i��rs�j
�U�j���ꂼ��̓d�r�̕K�v���́A
�@�@�@�⒮��́A
�@�@�@�@���d�r��370�~10![]() ��100=3.7�~10
��100=3.7�~10![]() �i�j
�i�j
�@�@�@�@��C�d�r��3,310�~10![]() ��100=33.1 �~10
��100=33.1 �~10![]() �i�j
�i�j
�@�@�@�ʔ̂́A
�@�@�@�@���d�r��77�~10![]() ��14=5.5�~10
��14=5.5�~10![]() �i�j
�i�j
�@�@�@�@��C�d�r��180�~10![]() ��14=12.9�~10
��14=12.9�~10![]() �i�j
�i�j
�V�j���ꂼ��̓d�r�̕K�v���́A
�@�@���d�r��(3.7+5.5)�~10![]() ��9.2�~10
��9.2�~10![]() �i�j
�i�j
�@�@��C�d�r��(33.1+12.9)�~10![]() ��46�~10
��46�~10![]() �i�j�@
�i�j�@
�W�j�Вc�@�l�d�r�H�Ɖ�̎������A�⒮��p�Ƃ���2004�N�̋�C�d�r�̍��������o�א���(32,237���)�ƗA��
�@�@���ʁi�����ȁA�f�Փ��v�ɂ���9,590��j����������C�d�r�̑��ʂ́A
�@�@�@(32,237+9,590) �~103=41.827�~10![]() ��41.8�~10
��41.8�~10![]() (��)�ł���B
(��)�ł���B
�@�@���̐��l�ƂV�j��46�~10![]() �i�j���r�����10���̌덷���d�r�o�ׂ̂ق������Ȃ��B
�i�j���r�����10���̌덷���d�r�o�ׂ̂ق������Ȃ��B
�@�@�����̉���̐��x�����l������Ώ�L�̐����͂��Ȃ�g�������Ɏv����B
�@�@�덷�����⒮��Ɏg����d�r�̑��ʁ��d�r�̏o�ב�����46000/41827�~100=110.0(%)
�@�@�덷����10(��)�ł���B
�@�@���d�r�́A�⒮��Ɏg���鐔�ʂ͋ɂ킸���Ȃ��ߊ��d�r�̏o�א��ʂ��琄�肷�邱�Ƃ͑S���s�Ǝv����
�@�@�̂ŏȂ����B
�X�j���_�@
�@�@�䂪���ɂ�����⒮��̉ғ��䐔�͖�144����A�ʔ͖̂�35����A���v��180����Ɛ����ł��܂��B
�@�@�⒮��p�̋�C�d�r�͔N��41,827����i41.5�~10![]() �j�o�ׂ���46,000��������Ă���Ɛ����ł��܂��B
�j�o�ׂ���46,000��������Ă���Ɛ����ł��܂��B
10�j��L�̂悤�ɕ⒮��̉ғ��\���䐔���Z�o����̂ɑ����̉���������B����A�����̉���̈����
�@�@���x���グ�Ă����Ε⒮��̎��ғ��䐔�Ɠ�Ґl���ɑ��镁�y�������߂邱�Ƃ��\�ł͂Ȃ�����
�@�@���l���Ă��܂��B
�@���肪�����P�̐��l�������ω�������Ɨ\���l�͑啝�ɕς���Ă��܂��܂��B
�������A�⒮��̏o�ב䐔�y�ы�C�d�r�̏o���͐��m�Ȃ̂ŁA�����̐��l�𒆐S�ɂ��ᔻ��
�o��̏�ŗ\���������܂����B�����̉�����e���ʂ̕��X�̂��ӌ��A���m�����������������ł�
���x���グ�����Ƒ����܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Q�O�O�T�N�S���Q�O����