水野のサイト
応用情報技術者試験
●平成21年度秋期試験 午後問題 問2
「文字列照合処理」
【解説】文字列探索の、逐次探索法とボイヤー・ムーア法についての問題です。 この二つのアルゴリズムの考え方と、プログラム作成および実行効率評価の能力が問われています。
【設問1 解答】
| ア | T.length - P.length + 1 |
| イ | P.length |
| ウ | P.length - j |
【設問1 解説】
問題文の図1、2より、i はテキスト文字列Tの添え字であり、パターンPと照合する位置を示しています。 したがって、その最大値(ア)は
j はパターンPの添え字です。Pのすべての文字を対応する位置のTの文字と比較しています。 したがって、j は P の先頭から最後までを指しますので、(イ)は P.lengthとなります。
D[k]には、パターンPのj番目の文字に対するスキップ数を入れています。 スキップ数は、「判定文字と一致するパターン内の文字が、テキストの判定文字に対応する位置に来るように」決めます。 つまり、下図のように
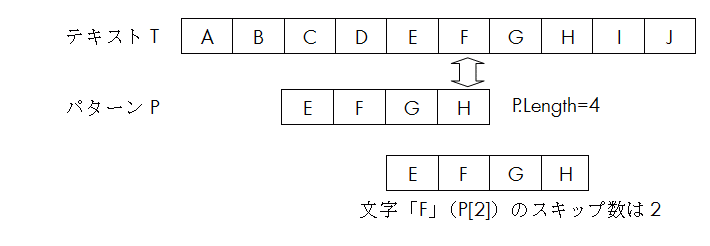
【設問2 解答】
| エ | 10 |
| オ | 6 |
【設問2 解説】
上記のように、パターンの j番目の文字に対するスキップ数は
パターン内に同じ文字が複数ある場合は、「パターンの末尾から最も近く(ただし、末尾を除く)にある」文字をとります。 文字「P」は、パターンの3番目と5番目ですから、5番目の方で考えます。すなわち、
【設問3 解答】
| α | 12 |
| β | 8 |
【設問3 解説】
αの位置では、最初にテキストの最初の3文字「PIC」とパターン「PEP」を比較します。 この場合、2文字目(αの2回目)の
「効率的な照合方法」では、まずスキップ数を求めます。 「P」のスキップ数は2、「E」のスキップ数は1、その他の文字のスキップ数は「3」です。
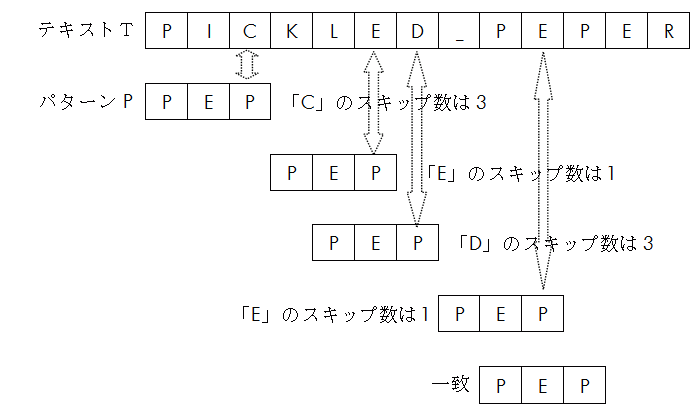
 このページの先頭
このページの先頭